
豚と共に生きる日々
命への感謝を胸に、
肥前さくらポークを育む
山中 真二 [唐津市肥前町]
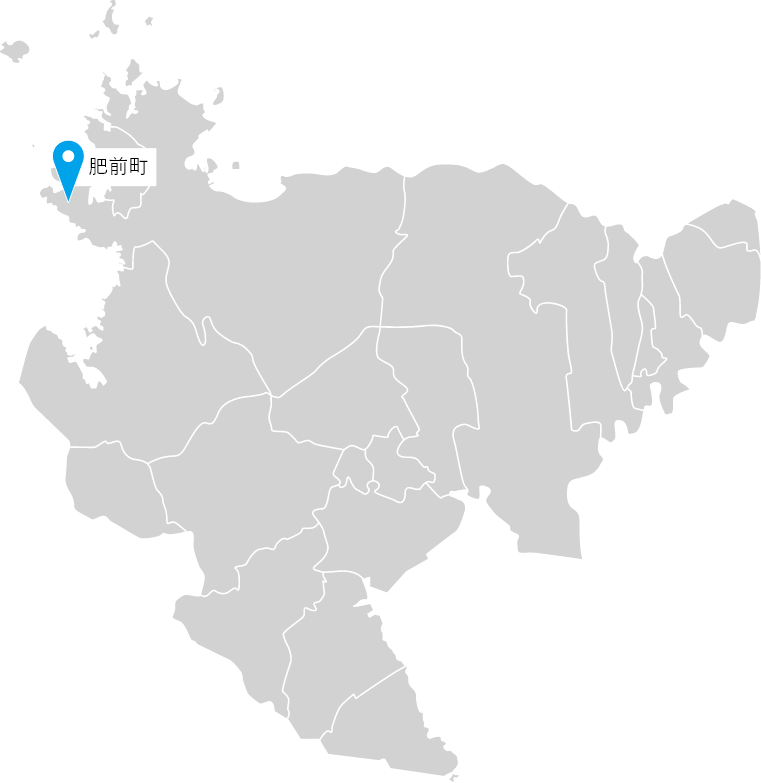
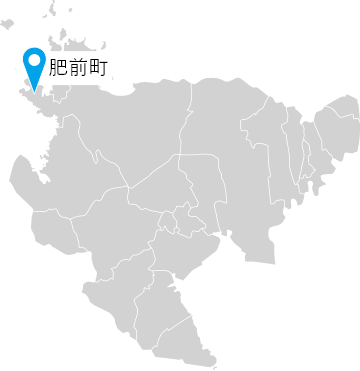
- INTRODUCTION
- きめ細かな肉質、柔らかな食感、とろけるような脂の甘さで多くの人を魅了するブランド豚「肥前さくらポーク」を生産している、佐賀県唐津市肥前町の山中真二さん。祖父が始めた農場を29歳で継いで以来38年、日々まっすぐに豚たちと向き合いながら、感謝の気持ちを大切にして養豚に取り組んでいます。
豚がそばにいる暮らしが私の原点
気がついたら、そこに豚たちがいる。それが、私の生まれ育った環境です。養豚は祖父の代から続いており、私自身も幼い頃から小さな豚舎の中を通ったりして生活していました。小学生になると繁殖用の豚舎に入り、子豚が生まれれば体を拭き、温め、お母さん豚のミルクを飲ませる。これが私の中に残る最も古い養豚の仕事の記憶です。
昭和55年、構造改善事業によって現在の農場が整備されました。その後、父の死をきっかけに私が本格的に養豚を引き継ぐことになります。現在では人工授精を導入し、より安定した繁殖体制を確立。母豚250頭を基盤に、年間およそ5000頭を出荷する一貫経営へと発展しました。
1995年頃に「肥前さくらポーク」のブランドが立ち上がって以来、私たちも指定養豚農家として出荷を続けています。このブランドで育てるのは三元豚と呼ばれる交配種。繁殖力の高いランドレース種をベースに、病気に強い大ヨークシャー種、そして肉質の良いデュロック種を掛け合わせた、いわば“いいとこどり”の豚です。
豚肉の味を左右する大きな要素のひとつが、飼料へのこだわりです。ビタミンやミネラルを豊富に含む海藻粉末や麦類を、豚の成長段階に合わせて配合した飼料を使用しています。ペレット状に加工したり、加熱処理したりと食べやすく工夫された飼料により、豚たちはしっかり育ちます。その結果、肉の色合いは美しく、甘みと柔らかさが増し、臭みの少ない仕上がりになるのです。

「極上」は、基本を積み重ねた先にある
昔はすべてが手作業でしたが、今では糞尿の処理や給餌など多くが自動化されました。それでも、何より大切なのは“人の目”です。まずは餌。与えるだけでなく、ちゃんと食べているか、吐き戻していないかまで見届ける必要があります。それから毛並みにも重要なサインが隠されています。艶がない、逆立っているといった様子があれば、体調に異変があるかもしれません。加えて、行動の観察も重要です。たとえば母豚が発情期に入ると、通常は頭を上げて檻に体をぶつけるような仕草をします。そういった動きが見られず、じっとしているようなら何らかの異常が考えられます。大切なのは、そうした“いつもと違う”を見逃さないこと。私は一緒に働く息子にも「とにかく豚の“動き”をよく見なさい」と伝えています。
私たちは、特別なことをしているわけではありません。大事なのは、とにかく基本を丁寧にやり続けることです。水や餌を与える、掃除をする。それらをただの作業としてこなすのではなく、常に豚の様子に目と心を配りながら取り組むことが大切です。そうした日々の小さな積み重ねこそが、健康で良い豚づくりにつながっていきます。
時代の流れとともに、餌の質が向上し、設備や環境も整ったことで、養豚全体のレベルは大きく向上しています。豚の骨格や体格も格段に良くなり、最高ランクである「極上」と評価されることが増えてきました。
昔は極上に選ばれる豚はほとんどなく、その割合は0.1%以下、ほぼゼロに近い時代もありました。しかし現在では、100頭出荷したうち約5%が極上に選ばれるまでになっています。品評会に出す豚は、最終的に自分の“目”で選定します。体型や筋肉の付き方をじっくり観察していると「これは極上になる」と確信できる瞬間があるのです。それは、毎日豚の姿を見続け、基本を一つひとつ丁寧に積み重ねてきたからこそ培われた、経験からくるものです。

後悔したくないから。責任と覚悟を持って命と向き合う
養豚とは、命と真剣に向き合う仕事です。たとえば衛生管理には、ほんのわずかな妥協も許しません。何千万円もの費用をかけてでも、ワクチン接種や清掃、消毒を徹底的に行っています。「あのとき注射しておけばよかった」などとは絶対に思いたくありません。後悔しないために、やれることはすべてやる。それが、命を預かる者としての責任だと考えています。
養豚において何より大事なのは、自分自身の「豚に対する思い」だと、私は感じています。私は豚のおかげでここまで生きてこられ、子どもを育てることもできました。“豚に生かされている”という意識が常に根底にあるからこそ「もっとよく見てあげよう」「より過ごしやすい環境にしよう」と自ずと考えられますし、何か異変があったときには、頭よりも先に体が動き、すぐに対応できるのです。豚を管理する“人の目”というのは、まさにそうした意識や愛情から生まれてくるのだと思います。
やがて出荷のときが来ると、30頭ほどをトラックに積み込みます。気がつけば、自分の口から「ありがとうな」と声がこぼれるのです。「この子たちが、これから社会に出ていくんだな」と思うと、胸にこみ上げるものがあります。計量所に着き、処理場へと入っていく姿を見送るとき、豚たちへの感謝をあらためて深く感じます。
経済動物と言ってしまえばそれまでですが、きちんと屠畜され、検査にも通って、立派なお肉として届けられる。それが、何よりありがたいことです。私たちが毎日の生活を送れているのは、やっぱり豚のおかげ。最後まで役割を果たしてくれた豚たちへの感謝は、どれだけ伝えても足りないほどです。これからも一頭一頭、大切に育てていきます。

- 山中 真二
- 養豚農家の3代目として29歳で農場を継承。現在はJAグループ佐賀県下養豚部会 部会長を務め、唐津市肥前町の農場で種付から出荷までを一貫管理し、ブランド豚「肥前さくらポーク」を生産。佐賀県畜産共進会での受賞をはじめ、高品質な豚づくりが高く評価されている。好きな豚肉料理は、脂の甘みを最も感じられる「しゃぶしゃぶ」。




